はじめに
退職代行モームリの家宅捜索が報じられ、非弁行為という言葉が急に身近になりました。何が合法で、どこからが違法か。線引きが曖昧なまま依頼すると、依頼者が不利益を受ける恐れがあります。
本記事では、非弁行為の基礎、今回の報道で何が焦点になったか、安心して使える退職代行の見分け方までを、初めての人でも迷わない順で整理します。なお、非弁行為の定義や注意喚起は弁護士会の公表情報を基に要点を整理しています。
・非弁行為の定義と退職代行で許される範囲
・モームリ関連の報道で注目された論点
・非弁リスクを避けるためのチェックリスト
・申し込みから退職完了までの実務フロー
・よくある質問のボーダーライン整理



ひろ、僕もうムリ。ニュースで「非弁行為」って見たけど、退職代行って本当に大丈夫なのかな?



おもち、大丈夫。鍵になるのはひとつ。「単なる意思の伝達=OK、会社と交渉まで=弁護士・組合」。この線だけ守れば、安全に辞められる。今日はそれをハッキリさせよう。
非弁行為とは何か(退職代行と弁護士法の関係)
結論
弁護士でない者が報酬目的で、法律事件に関する法律事務を取り扱ったり、その周旋をすることを非弁行為といい、弁護士法72条で禁止されています。退職代行は本人の退職意思を会社へ伝える伝達に限れば適法に運用できます。一方で、条件交渉や示談は弁護士領域です。
許される範囲(一般の退職代行の想定)
・退職意思の伝達
・貸与物返却や最終連絡手段など事務的連絡の伝達
・会社からの問い合わせの一次受け(伝達に限定)
弁護士対応が必要な場面
・退職日の調整や有給消化の条件調整など、合意形成を伴うやり取り
・未払い賃金や退職金、パワハラ慰謝料など金銭請求の交渉や和解案提示
・懲戒や損害賠償の通告への回答、労働審判や訴訟対応
これらは交渉に該当し、弁護士の業務に当たります。
補足
弁護士でない者が弁護士に法律事務を周旋する行為も非弁行為に含まれます。
ニュースで話題のモームリ関連:何が問題視されたか
要点の整理
・退職代行モームリの運営会社に対し、弁護士法違反容疑(非弁)で家宅捜索が実施されたと報じられました。報道では、報酬を得る目的で弁護士に法律事務をあっせんした疑いが焦点とされました。提携先の弁護士事務所も捜索対象と伝えられています。
・非弁行為の注意喚起は以前から公表されており、残業代や慰謝料、退職金、有給消化などの問題を退職代行業者が本人に代わって会社と話し合うことは非弁行為となり得ると明示されています。
非弁行為が禁止されている理由は、法的知識が不十分な者が介在すると権利が不当に切り下げられる恐れがあるためと解説されています。
退職代行の業務範囲:OK/NGの具体例
退職代行の可否目安
| 行為の例 | 一般の退職代行 | 弁護士 |
|---|---|---|
| 退職意思の伝達 | 可能 | 可能 |
| 事務連絡の伝達(返却方法や窓口) | 可能 | 可能 |
| 有給消化の条件調整 | 非推奨・非弁リスク | 可能 |
| 退職金・未払い賃金の交渉 | 不可(非弁) | 可能 |
| 損害賠償や懲戒への回答・示談 | 不可(非弁) | 可能 |
| 労働審判・訴訟の手続 | 不可 | 可能 |
団体交渉権を持つ労働組合型は対応できる場面もありますが、具体の範囲と実力は要確認。過剰な約束や万能感の訴求には注意。
安心して使える退職代行の見分け方
非弁リスクを避けるチェックリスト
・運営会社名、所在地、代表者、固定電話、企業メールの記載
・特定商取引法表記、利用規約、返金ポリシーの整合性
・対応範囲の明示(伝達のみか、交渉は弁護士が対応か)
・弁護士または弁護士法人の関与の仕組みが具体的に説明されている
・料金の内訳と追加費用の有無(成功報酬や紹介料の扱い)
・口コミは直近時期と具体性を重視。事業者の返信姿勢も確認
・誇大表現の排除。即日なんでも可能、成功率保証などは慎重に
入金口座の名義が運営会社と一致しているか確認。個人名口座のみ、海外送金のみなどは要注意。
後払いをうたう場合、条件や手数料、支払不能時の扱いで実質割高になる例があります。規約の定義を先に読む。
料金相場・支払い方式・トラブル回避術
相場の目安
・一般の退職代行(伝達型):おおよそ2〜5万円台
・弁護士対応(交渉含む):事案により上振れ
支払い方式ごとの留意点
・前払い:返金条件の明記と適用条件を確認
・後払い:与信条件、適用範囲、追加費用の有無を確認
トラブル回避の基本
・申込前に規約と特商法表記、返金条件を保存
・委任範囲を文面で明確化(伝達のみ、交渉は弁護士)
・不払いが疑われる場合は労基署や弁護士への相談を早めに検討
・一般代行に交渉を求める
・口頭の約束だけで申し込む
・会社からの条件提示に代行担当が応答し続けて交渉化させる
実例で学ぶ:相談から退職完了までの流れ
初回相談から申込
雇用形態、希望退職日、有給残、未払いの有無、機器返却の方法をヒアリング。交渉が必要になった場合の弁護士連携を事前説明。申込時に委任範囲と返金条件に同意。
会社連絡(伝達)
退職意思と返却手順、連絡窓口の伝達に限定。会社が条件のやり取りを求めてきたら、そこで伝達を止め、弁護士へ橋渡し。
アフターケア
離職票、健康保険、年金、年末調整の案内。未払いが疑われる場合は証拠保全を促し、労基署や弁護士相談を提示。
非弁行為の枠外に出ない運用が安全。交渉になりそうな気配を感じたら即エスカレーション。



ひろ、有給を全部取りたいって伝えるのは大丈夫かな?
なんかそれもダメって言われそうで。



大丈夫だよ。希望を“伝えるだけ”なら問題ない。でも「会社に認めさせる」みたいな交渉になると、それは弁護士の仕事になる。だから伝達で止めて、必要なら弁護士にバトンを渡すのが安全なんだ。



なるほど、線引きがだいぶ掴めてきた。
伝達はOK、交渉は弁護士。覚えたよ。



うん、それさえ守れば安心して動ける。焦らず、安全設計でいこう。
よくある質問(FAQ)
- 非弁行為のボーダーラインは
-
合意形成を目指す条件のやり取りは交渉に該当し、弁護士領域です。意思の伝達にとどめれば非弁リスクを避けやすいです。
- 有給消化や退職日の調整は依頼できるか
-
調整は交渉の要素が強く、弁護士対応が原則です。希望の伝達までに限定する体制を選びましょう。
- 会社が損害賠償を示唆してきた
-
示談や回答は弁護士へ。一般代行が応じると非弁行為の恐れがあります。
- 弁護士への周旋も非弁行為か
-
弁護士でない者が報酬目的で法律事務を弁護士に周旋する行為も非弁行為に含まれます。
- 今回の報道で最も見落としやすい点は
-
伝達と交渉の分離だけでなく、周旋や紹介料の取り扱いが非弁該当性の論点になり得る点です。
全体の注意点・チェック・NG行動
・交渉は誰が担うかを事前確認(弁護士かどうか)
・特商法表記、利用規約、返金条件が整っているか
・料金の内訳と追加費用、入金口座名義の一致
・後払いは条件次第で実質割高になることがある。規約の実費や手数料定義を確認
・口コミは直近時期と具体性、事業者の返信姿勢を重視
・誇大表現や万能アピールに流されない
・記録を保存(規約、領収書、チャット、メール)
・一般代行に交渉を依頼する
・口頭約束だけで申込
・会社の条件提示に代行担当が応答し続けて交渉化させる
まとめ(結論)
結論
退職代行は伝達に限定すれば安全。交渉や示談、そして報酬目的の周旋は弁護士領域であり、ここを越えると非弁行為の恐れがある。報道で不安が高まった今こそ、運営情報の透明性、規約、返金条件、弁護士連携の仕組みを確認し、体制が明確な事業者を選ぶ。
・非弁行為は弁護士法72条が禁じる行為。伝達はOK、交渉は弁護士
・モームリ報道の焦点は周旋や交渉関与の疑い、表示と実態の整合性
・非弁リスク回避は、運営情報と規約、返金条件、弁護士関与の明示確認
・実務は伝達と交渉の切り分け、交渉化しそうなら即エスカレーション

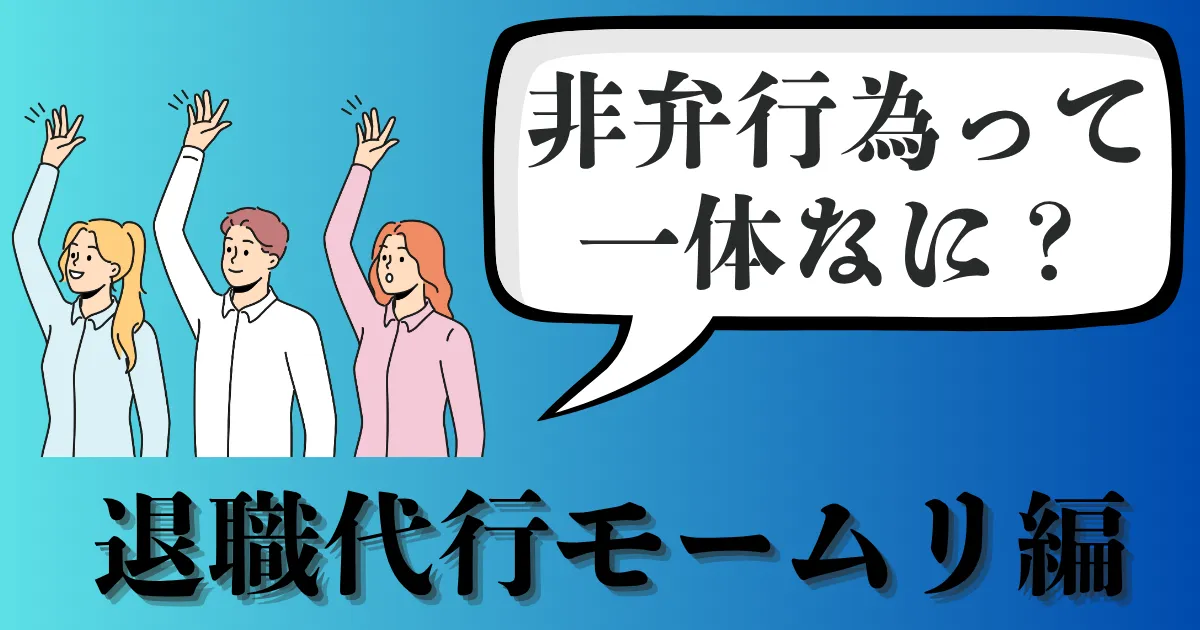
コメント